〇〇力という呪い~③コミュニケーション能力について~
前回は、「これまでの日本人が身につけてこられなかったために不利益が生じてきた能力、それを子どもだけに背負わせるのはどうなのか」と、若干自分を含めた大人の姿勢についての問題提起をしたつもりでした。
今回お話させて頂きたいのは、「コミュニケーション能力」ということについて、です。
いろいろな定義があるコミュニケーションですが、通常思いつく範囲でいえば「意思疎通」ということばに集約できるでしょうか。(いろいろな定義があるものを国が独自に定めて、それを全員に適用するということに、若干違和感を禁じ得ないのですが、そこについては述べません)
こういうときは文部科学省の見解を見るしかないので、ホームページから「有識者会議による」定義の抜粋をさせて頂きます。
『「Aいろいろな価値観や背景をもつ人々による集団において、(中略)人間関係やチームワークを形成し、B正解のない課題や経験したことのない問題について、対話をして情報を共有し、自ら深く考え、C相互に考えを伝え、深め合いつつ、合意形成・課題解決する能力」』※A~Cについては筆者がつけたものです。
一応この定義に基づいて各施策を実行している、ということのようです。違和感を覚える部分がないではないですが、まずはこの定義から
求められる人物像・養うべきスキル
というものは見えてきますので、一つ一つ私見を述べていきます。
1.多様性を理解し受容することのできる能力
前提といえる「Aいろいろな価値観や背景をもつ人々による集団」の中でのコミュニケーションということを考えますと、たとえば国籍であったり、肌の色であったり、性自認であったり、世代であったり。こうした人ごとに異なるバックグラウンド・努力や時間で変化させることのできない属性を「理解しようとする姿勢」がまず不可欠と言えるでしょう。ホロコーストの例をたどるまでもなく、多様性の対義語は画一性であると考えられますが、惨劇を生むのみならず、このことは思考の硬直化と自己正当化、そして排除の力学を生じさせます。2018年には、65歳以上の方々の人口に占める割合が28%を越えました。また、合計特殊出生率は微増とはいえ欧米を下回る1.44人(2016年)とされています。とみに報道されることでもあるのですが、先進国の中でも例を見ないほど日本の人口は急激に減少することが確実視されており、それは世代間負担もより厳しい差が生じるということでもあります。
1992年から減少し続けている生産年齢人口が上向くことは、このまま自然増を待つだけではありえないことから、日本国内は今後どうやっても他国の人たちを受け入れていかざるを得ません。これは政治的主張ではなく、この経済・生活水準を保つという前提にたてば物理的に導かれる帰結です。現実をみるというのはそういうことではないでしょうか。生活水準を下げるということも、国の規模もシュリンクさせていくということも、考え方としてはあるでしょうが、合意が得られていない以上仮定の話を続けても仕方ありません。その方向性の話こそが政治であると思いますし、示された民意によって決めていくべきです。
少し話がそれてしまいましたが、いずれにせよ排除の力学が働くことは際限ない排除を繰り返す危険をはらみ、結果的に孤立につながることでもあります。そこで戦略的に「排除の力学こそを排除」していく必要があります。その認識にたてば、「いろいろな価値観や背景をもつ人々による集団」の中で、互いを理解しようとする姿勢、積極的に受容の姿勢を表明することが最低限必要であることは論を俟たず、文科省のあげた定義における現実認識は正しいといえるでしょう。
2.考え方の柔軟さと、そのために必要なフレームワークの構築
「B正解のない課題や経験したことのない問題」に対処するということは、大学入試センターが新たに導入する「大学入試共通テスト」に関してこう述べているところと符合します。「予見の困難な時代の中で新たな価値を創造していく力を育てることが必要です」という部分ですね。
これについて、これまで受験産業にどっぷり浸かってしまったわたしが申し上げるのはお恥ずかしい限りですが、大学入試共通テストの施行調査などを見ていますと、「ああ、今までと大して変わらないなぁ」という印象です。なぜか。元も子もない言い方ではありますが、学校の先生方とは異なり、塾でものを教えるというのは文字通り「未見の問題に対処する」ということだからです。
若干コミュニケーションと離れるかもしれませんが、入試問題は通例は同一のものが出されることはありません。そうでなければ「過去問集」など必要ないことからも明らかです。ではそこでどう考えてわたしどもが動いているかと申しますと、
例 過去問の中身を見ることで、その学校や試験に求められる知識の運用能力を正確に講師が把握する
➡これは、当然といえば当然なのですが、「4択問題がほとんど」とか、「記述は100字ぐらい」といった「誰が見てもわかる」ことを把握するのではありません。
例えば英語であれば、「要約問題…例年およそ●●語の英文から〇〇字の和文にまとめさせているということは、本文の抽象度を基準にして△段階までに分けさせていることがわかる」とか、「論理構成上、段落内の因果関係を見抜き、それを他の段落でも援用しているものが選択されている/もしくはあえてそうした一貫性を持ったものでそろえていない」など、出題側が求めている抽象的思考処理能力のレベルの判断です。
柔軟性というのは、これが例えば語数やテーマの全く違う英文で課されたときに、または設問自体が変えられてしまったときに、慌てずこれまでの思考方法を適用できているか、ということに集約されます。こう申し上げると「一つの考え方に凝り固まるのか」というお叱りを受けることもあるのですがむしろ逆です。決まった作法を、それも限界まで汎用性を高めた作法を身につけ、それを他の考え方や事態に合わせる訓練をすることで、比較対照することが可能になり、結果として常に同じ手順でもれなく(MECE)要素を分解でき、合理的に対応することが可能です。
これが文章で実現できなければ、より複雑な「人間関係」であったり、「チーム」の中であったりと、そうした変数の大きなフレームの中で通用するはずがない、というのがわたしの持論でもあります。
「フレームワーク」という言葉も業界や分野で定義が若干異なるようですが、一般論としては「思考の枠組み」ということができるでしょうか。文系科目や理系科目に限らず、学習が学習たるためには、このフレームワークがなければならず、学習が単なる文字列の暗記や手の運動になってしまう危険性すらあります。
例えば「〇〇大学△△学部では■■年に××の知識が問われた」ということを知るのは単に「事実を知った」ということにしかなりません。それなら生徒が一人でできるわけですから、塾や学校は必要ないことになってしまいます。
「フレームワーク」というのは、学習においては「正しい手順」と言い換えてもよいでしょう。例えば未知語の処理方法であったり、文章の形を利用することであったり、文字列・数式のパターンを見抜くためにどういう手順を踏んでいるか、常に同じ順序で考えていく、等々です。この「フレームワーク」というものは人間のコミュニケーションにおいては不可欠であると考えるのです。
なぜかと申し上げるならば、いつも初対面の人と出会ったときに同じフレームワーク(手順)で接していくようにすれば、「公平」で分け隔てなくすることが大切だと気付けますし、いくつかの失敗を経てリスク回避のための知識が蓄積できていくでしょう。そのフレームワークが完全なものではなく、常にアップデートしていく必要があるということに気づくには、逆にフレームワークが必要だということになります。若干逆説めいてはいますが、「軸がなければ、逆にぶれたままで、流されるままで人間関係を『浪費してしまう』」ともいえるかもしれません。「一期一会」ということばがあるように、人と人とのコミュニケーションというのは一回一回が本来は非常に貴重なものであるはずです。
また、フレームワーク、これは便宜上の「手段」にすぎないわけですから、常にアップデートが必要なのは言うまでもありません。文化、性別、価値観の違いはあって当然です。そうしたときに、これまでの考え方、手順を変更していくという柔軟さは人間関係において必須のものですし、合意形成のときにもなくてはならないものだと考えます。
3.独善的ではなく互恵的価値観の涵養
「涵養」という表現を用いたのは、価値観というものを教育の枠組みだけで身につけたり修正したりすることは事実上困難であるからです。「考え方・手順」はやり方さえ間違えなければいくらでも修正でき、アップデートしていけます。これは年齢などにはかかわらないと思っています。
ただ、価値観というのはぼんやりとしたものです。快不快の線引きをどこにするか、というレベルから、一つの事象がもつインパクトをどこからどこまでにするか、などです。すくなくとも視野狭窄に陥ることがないように、教育者はさまざまなことに腐心しなければなりません。
文部科学省の定義に戻りますと「C相互に考えを伝え、深め合いつつ、合意形成・課題解決する能力」とあるのですが、これは場といいますか、前提となっているのが前段の「いろいろな価値観や背景をもつ人々による集団」ということですから、正直できることとできないこととに分かれるようにも感じています。その「集団」がどう構成されているか、というのがとても大切なファクターです。むろん、「合意形成・課題解決」という表現から読み取れるように、ここにはある程度の妥協が含まれることを前提としているのでしょう…。
例えばエスノセントリズム(自民族優越主義)ということが言われたときに、「誰を主語にするか」というのは非常に繊細な問題でもあります。他にも「ジェンダー」がテーマとして浮上してくれば、それは善や悪といった二項対立で語れるわけでもなく、国ごとに基準や実態も異なりますし、当事者がいない場合の議論がはらむ瑕疵に気づくのはなかなかに困難だと考えられます。
つまり、合意形成や課題解決へ「向かう」ためにどうした意見調整をするのか、そのときに誰を主語にするのか、という難しさが常につきまとうであろう、と推察されるのです。
この合意形成や課題解決といった「結果」だけにこだわってしまえば、だれもが自分の今まで経験した中で無理やりに答えを出す場合も生じてきてしまうでしょう。それは「コミュニケーション」ではなく現状の追認にすぎません。集団が均質的であれば、それは誰にとって都合のよい答えであるかが検証されることもなく、次からも結果を出すことが目的となってしまいます。それは「深めあう」こととは真逆ですし、「相互」という言葉の意味がなくなってしまうことでもあります。
そう考えた結果、ひとつの仮説を提示したいと思います。文科省の定義からは「結果も大事だがそこに至るまでのプロセスをこそ大事にせよ」ということが導かれるのではないか、ということです。
そこで③で挙げたように、「独善性」を排しつつ、「互恵的」関係の中で意思決定をする、ということを重視できるようにする、と考えます。むろんそのような教育であってほしいという希望的観測もないではありません。
互恵関係においては、いうまでもなく利他的であることと利己的であることとの按分を常に考える作業が必要です。こういうと「妥協」になりがちですが、互恵が指すのはそこではないと考えるのです。例えば「駅の見学をして構造のあるべき形について考える」というテーマが設定されたとします。このときに、例えば集団内に、足を使って歩くことのできる人ばかりであれば、車いすの方々や白杖を持った方々の存在や動線までは考えられても、細部(床の素材、傾斜、またはどこで歩く人たちの速さによって自制を強いられているか、など)についてはなかなか考えられないのではないかと感じます。それは無理のないことです。経験に基づく実感がない限り、人はそう簡単に柔軟な思考はできないものです。そうではなく、「いま、議論しているわたしたちの集団の考えの多様さに、限界があるのではないか?」などの問いを立てることを許可すればよいのです。わからない、知らないことはほかの人に聞けばよいのです。人の意見を求めることなく、全く自分の考えを改めることのない「万能」な人間などいるはずがないのですから。
そう、場合によっては自分を問い直し、コミュニケーションも外に求める、「集団」自体をアップデートするといったような考えを指導者ふくめ、集団がみなで持っておくのも大事なことではないかと思います。また、駅の例を考えてもわかるように、互恵というのはあくまでも「互いの」利益を考える姿勢です。まるで「利己的でなければ自分に得がないではないか」という幼い思考をする人も残念ながら一定数いますが、他人を利することが自らを利することになる、そのようなケースは少なくないはずです。エレベーターは目の不自由な方だけでなく、わたしのように体力のないサラリーマンにもありがたい存在です。手すりが要所にあることは高齢者のためにもなります。車いすでも余裕をもって入れるほどトイレが広くなることで、不利益を被る人がいるでしょうか。
歴史に学ぶところがあるとしたら、最大の意義はそこにあるのではないでしょうか。歴史は、過去と現在と未来、ベクトルでも単なる線分でもなんでもかまいませんが、「一方向」に進化してきたと考えるのではなく、過去の過ちや、逆に成功体験を現在に活かすべきです。その意味では、現在のわれわれの取り組みも後の世代が何か考えるためのきっかけとなっているのかもしれません。たとえ失敗(というよりも結果が出せなかった取り組みなど)だとしても、それは後の世代が何かを検証するときの材料にもなるでしょう。
とまれ、一人で思考する、協働する、挫折する、失敗する、感情的しこりが残る、結論を出す、修正する…これらは全体が一つのプロセスでもあり、同時にその時々で重要な教育の機会でもあります。そういったことを、「互恵」という観点から見つめなおすことは、子どもたちにとってより深い考え方、可能性を見出すチャンスになると考えられるのです。
*** *** ***
大変長くなってしまいました。「額面通り」受け取るのなら、文部科学省の挙げた「コミュニケーション能力」の定義は歓迎すべきものだと考えます。ただし、それにはいかなる利害関係(政・官・業)とも自由であれば、という前提が必要です。そこの部分を調整する、明確にバイアスがないことを証明できるのは、子どもたちではないはずです。そしてバイアスがない、フラットな世界をめざすべき子どもたちに偏見が根付き、何か大変な事態を招いたとしたら、それも大人の責任であることは言うまでもありません。子どもたちは、生産された製品ではないのですから。
教育に手を入れる、アップデートしていくのは必要なことです。そこに異論をさしはさむ余地はありません。しかし、そのプロセスが仮にある利益相反行為を必然的にはらむものであったり、誰かが個人的な「大義」を果たすためのものであったりした場合、それは差し戻してゼロにする。それも大人の責任です。大人の責任というのは、かように重く苦しいものです。自戒をこめて、今回はここまでとさせていただきたいと思います。
講師:粕川優治

究進塾副代表。文系大学受験、および日大内部進学コースの責任者をしております。







 Twitter
Twitter YouTube
YouTube LINE
LINE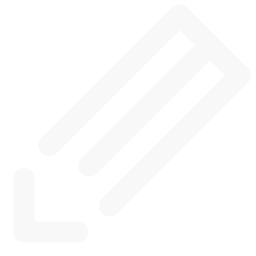 体験授業申込
体験授業申込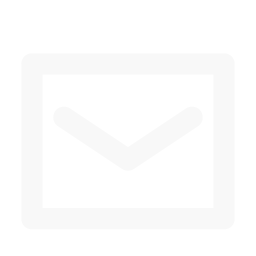 お問い合わせ
お問い合わせ