【日大付属】高3-4月 基礎学力到達度テスト 英語の問題構成と学習方針
皆さん、こんにちは。
今回は、基礎学力到達度テストの高校3年生、4月の英語試験について解説していきます。
「高校3年生ぐらいにあるテストなんだろうな」では、甘いです。
新学期が始まった瞬間に実施される試験ですから、「高2の学年末とほぼ同じようなもの」と思って対策しないと、現在1年生だったとしても、時間的な余裕があるとは全く言えません。
勉強を始めるなら、今すぐにスタートしましょう。
皆さんの基礎学対策の初めの一歩となれるよう、問題の傾向、学習の方針、やり方について説明していきたいと思います。

早稲田大学教育学部英語英文学科卒。 第二言語習得法に基づいた音読を重視した英語指導法が特徴。TOEIC945点。英検1級取得。日大付属生への指導経験も豊富で基礎学対策に精通した講師です。☆基礎学対策の詳細はこちら
【日大付属高校-基礎学対策】夏期講習(集団授業)開催のお知らせ
期間:8月1日(火)~8月18日(金)
開講科目:英語/現代文/古文・漢文/理系数学/文系数学
詳しくは下記バナーをクリック!
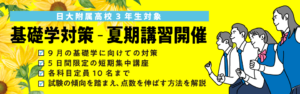
※こちらの講習は終了しました。
問題の傾向
出題内容
高3学年、4月の基礎学力到達度テストに出題される大問を参考に、出題傾向を見ていきます。
全部で7つの大問があります。
1.リスニング <12点>
2.語彙(短文読解)・熟語 <12点>
3.文法 <10点>
4.語句整序 <8点>
5.会話文 <8点>
6.グラフ読解 <24点>
7.長文読解 <26点>
大問2:語彙(短文読解)
説明文から単語を推測し、解答する問題です。イメージできない方は実際に過去問を見てみることをおすすめします。
大問6:グラフ読解
グラフと、グラフに関係する文章があり、それを参照しながら問題に答えていくタイプの問題です。
大問7:長文読解
オーソドックスな、いわゆる”長文読解”です。
問題の傾向
問題の傾向として、3つの特徴が挙げられます。
①まんべんなく出題される
②英検3から準2レベル
③正確な読解力が必要
細かく見ていきましょう。
①満遍なく出題される
1つ目の傾向は「満遍なく出題される」ことです。
過去問を分析してみて、「これだけやっておけば大丈夫」というコツを見つけたかったのですが、残念ながらありません。
なぜかというと、
リスニング
語彙
文法
語句整序
会話文
グラフ
長文読解
とにかく色々な角度から英語力を試す問題が出題されます。「ここだけ対策しておけばいい」というテストではありません。
この「満遍なく出題される」というのは、「そうか、満遍なくなのか」と軽く受け止めてしまうと危険です。
例えば、学校の先生に「次のテストの出題範囲は、今までやったことを全部」と言われた、とイメージしてみてください。
かなり危機感を感じてもらえると思います。
普通のテスト:限られた単元が範囲
基礎学テスト:これまでやったこと全部が範囲
「今までテストごとにその場しのぎの勉強だけをしてきた」という人にとっては結構危険なテストです。
初めに述べたとおり、早めにスタートしないと間に合わない可能性が高いです。
②英検3から準2級レベルが出題される
基礎学力到達度テストの出題レベルは「英検3~準2級レベル」となっています。
英検のレベルは、
・英検3級=中学3年生くらい
・英検準2級=高校2年生くらい
つまり総合的に、中学3年生~高校2年生くらいまでの範囲です。
英検3級くらいのレベルがあれば、一応いくらかは得点を稼げます。
ただし、
大問6「グラフ読解」
大問7「長文読解」
ここに登場する単語や文法は、英検準2級ぐらいのレベルの問題です。
つまり、英検3級どまりの英語で挑むと、大問6の24点 + 大問7の26点分=半分近くの点数を、ごっそり落としてしまう可能性があります。
目標レベルはココ!「英検3級~準2級レベル」と言ってはいますが、きっちり点数を取りたいと思ったら、準2級レベルの英語力までは持っていきたいところです。
③正確な読解力が必要
特に「会話文」の出題内容を見ると、選択肢が結構紛らわしいものになっています。
簡単に絞れるもの、というより、正確に読解できないと引っかかってしまう選択肢が出されています。
ます。
確実に点数を取るためには基礎学でしっかりと点数を取るためには、
「なんとなく単語や文法や単語だけで読んでいこう」
ではなく、
しっかりと単語と文法を固めて、正確に読んでいく必要があります。
目標レベルはココ!
具体的な学習方法
では、対策をするときに何をしていけばいいのかを、具体的にみていきます。
①スタートラインを設定する
基礎学の場合、「身に着けるべきレベル = ゴールライン」はすでに決まっています。
英検準2級くらいまでのレベルが出題されるテストですから、「英検準2級のレベルの英語力を身に付けること」がゴールラインです。
ただし、スタートラインは人によって違います。
まず自分に合ったスタートラインを設定するということが大事です。
スタートラインは人によります。例えば「高校2年生だけど中学レベルの英語ができていない」という人は、中学レベルからスタートすることが必要になります。
また「中学レベルはできているけど、高校1年生あたりのレベルのところからはわからない」という人は、高校1年生くらいのレベルからスタートする必要があるわけです。
でも、「じゃあスタートラインをどうやって設定すればいいの?」と思う方もいるはずです。
| 💡細田先生のおすすめ「スタートラインの探し方」💡
1つおすすめな方法は「英検過去問を音読、和訳すること」です。過去問は、英検のホームページに掲載されています。しかも、5級~1級の問題まで、全ての級の過去問が載っています。このうち、1番下の級 = 5級から音読と和訳をしていきます。 (例) |
このように、英検を下のレベルから音読・和訳をしていき、自分が「つまずいた」と思うところを学習のスタートラインにしていきます。
この方法で、みなさんそれぞれのスタートラインが設定できます。
②学習法を見直す
ゴールラインとスタートラインが決まったら、走り出す必要があります。
ただし、「どう走り出すか」が問題です。
日常生活でも、スタートからゴールに向かう際に「走る・自転車・電車・飛行機」というように、どういう手段を使ってゴールに向かうのかはそれぞれの自由です。
つまり、「どのような学習法を選んで、基礎学の目標点数つまりゴールラインに達するか」は、その学習者次第なんです。
もし今、あまり正しくない勉強法をしているとすれば、学習法を見直す必要があります。その方法だと、目的地にたどり着けない可能性があるからです。
| 💡細田先生のおすすめは「音読」💡
特におすすめなのが「音読」です。 音読は、ものすごく優秀な学習法なんです。これ1つやるだけでも英語力がどんどん伸びていくような学習法です。 「音読をしていない人」と比べたら、「音読をしている人」の方が何倍も速いです。それこそ走っている人と、電車で行っている人くらい差があります。 |
音読に限らず、学習方法をきちんと見直してからスタートするということが大切です。
③今すぐ始める
あとは「一歩踏み出すということ」です。
・ゴール
・スタートライン
・学習方法
これが決まったら、今すぐ始めましょう。
「基礎学の点数を何とかしよう」と思っているから、この記事を読んでいるはずです。その勢いで始めてしまいましょう。
「明日やろうは馬鹿野郎」です。明日でいいかな、また今度にしよう、というのは駄目です。
「思い立ったが吉日」で、今すぐアクションを起こしていきましょう。
まとめ
皆さんが踏み出す最初の第一歩は、
〇スタートラインの設定
〇学習方法の見直し
〇今すぐ始めること
この3つです。
それでも「色々と疑問がある」「音読をどれくらいすればいいかよくわからない」など、色々考えてしまうと思います。
そういうときは、学校の先生、塾の先生など、誰かに相談しましょう。
究進塾では、マンツーマンで生徒1人1人に対して、その生徒に合った学習計画を作成し、確実に目標点数に到達できるよう、丁寧に指導していきます。
「どうしていいかわからない」「受講に興味がある」という方は、「無料体験授業をご希望の方」からお気軽にご相談ください。
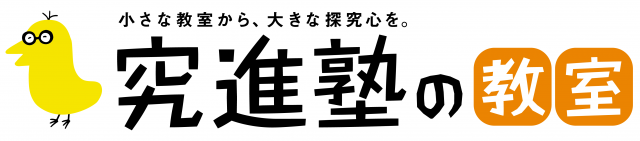






 Twitter
Twitter YouTube
YouTube LINE
LINE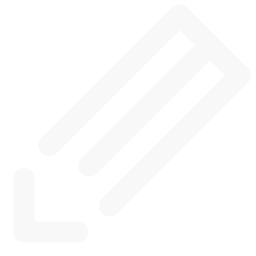 体験授業申込
体験授業申込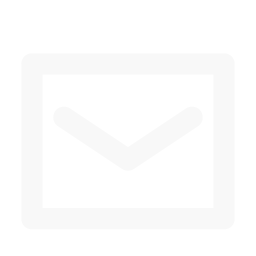 お問い合わせ
お問い合わせ