【高3-9月】 基礎学力到達度テスト 英語 大問1「リスニング」対策
皆さんこんにちは。今回は、基礎学の具体的な対策として、リスニング対策の解説をします。
リスニングというと、日本人は苦手な人が多いイメージがあります。
「リスニングは全然できない」
「できないし苦手だし、どうやって対策したらいいかわからない」
そんな皆さんのために、今回はリスニングの対策方法をご紹介します。

早稲田大学教育学部英語英文学科卒。 第二言語習得法に基づいた音読を重視した英語指導法が特徴。TOEIC945点。英検1級取得。日大付属生への指導経験も豊富で基礎学対策に精通した講師です。☆基礎学対策の詳細はこちら
リスニング対策は必要なの?
基礎学では「別に満点とか高得点を目指したいわけじゃなくて、最低限取れればいい」という人も、おそらくいると思います。
となると、リスニングの配点は20点なので、「最悪そこは落としてもいいかな」と思っている人も、結構いるはずです。
こういう場合もあるのに、そもそもリスニング対策というのは、すべきなのでしょうか?
💡細田先生の答え「絶対にした方がいい」💡僕の答えとしては、英語学習をする上で、リスニング学習は絶対にすべきです。
なぜなら、様々な研究で「リスニング力が伸びると、他の技能も伸びる」ということがわかってるからです。
リスニング対策をすると、リスニング力だけが上がるわけではありません。
・リーディング力
・スピーキング力
・ライティング力
こうした他の要素が上がったりします。
しかも、リスニング対策後に他の要素を勉強したとき、勉強の成長スピードが上がることもわかっているんです。
リスニング対策をした場合、単純にリスニングの点数が上がるのはもちろん、加えてその後にあるリーディングの対策もスムーズに進めることができ、英語学習の効率が全体的によくなります。
これが「リスニング対策は絶対にした方がいい」という理由です。
リスニングが出来ない原因は何?
リスニングは「できない」と思っている人が結構います。そして、そもそも「なんでできないのか?」ということがわかっていない人がとても多いです。
何でできないかがわかっていない
↓
どうやって直したらいいか、どうやってリスニング力を上げたらいいかがわからない
こうなるのは当然です。
| ?リスニングができない原因は一体何?
答えは、自分の発音と音源の発音が違いすぎるからです。 (例)「Some men are looking at the paintings on the wall.」 この例文を読むとき、多くの日本人が「Some / men / are / looking / at / the / paintings / on / the / wall 」のように、1単語1単語はっきりと読むと思います。特にリスニングがあまり得意じゃない人ほど、英語を1単語1単語で区切って、すごくはっきりと読んでしまう傾向にあります。
?ネイティブはどう喋っている? ネイティブは、辞書に載ってるような発音で、1単語1単語、全部をはっきりと喋っているわけではありません。無意識に色々な音の変化を起こしながら喋っています。 音声変化の詳しい話は割愛しますが、 (例) これらの音が繋がって発音されます。他にも「at the painting」では音が繋がってtの発音が消えたりします。 このように、 日本人が「こういうふうに発音するだろう」と思っている発音と、実際にネイティブの人がする発音には、ものすごく大きなズレがあります。 発音のズレが大きすぎると、同じ音だと脳が認識してくれません。 だから「Some men are」って言われたときに「サム メナーって何だ?どういう単語なんだ?」というように、全くわからなくなってしまうわけです。
|
リスニングができない人の1番の原因は、「実際に流れてくるネイティブの音」と「自分の思ってる音(特に自分の発音)」がズレすぎてしまっていることが原因です。
実際に音声を聞いて実験してみたい方は、こちらの動画でチャレンジしてみてください。
リスニング力を上げるには?
では実際に、リスニング力を上げるにはどうしたらいいのでしょうか。
💡細田先生の答え「音源と同じ発音を目指せ!」💡リスニング力を上げる方法は、実はこれは非常に単純です。「音源と同じ発音を目指せばよい」です。
ネイティブの発音と自分のイメージする発音にあるズレが原因ならば、ネイティブの発音と自分の発音が同じになればいいわけです。
完全に同じである必要はありません。でも、近づけば近づくほどいいです。自分の発する音と聞こえてくる音が同じになれば、どんな単語が使われているかが認識しやすくなります。
リスニング力を上げたいと思ったら、ただ音を聞くのではなく、自分の発音を音源と近づけていく練習が必要です。
リスニング力を上げる学習法とは
では「具体的にどうやったら、自分の発音を音源と同じようにできるのか?」を解説をしていきます。
具体的な学習法2つをご紹介します。
1. シャドーイング
最近は、聞いたことがあったり、学校でやったことがあるという生徒も増えてきている方法です。
シャドーイングは、リスニングにとって「最強の練習法」というくらい優秀な学習法です。
やり方は、音源の後を影のように付いていく練習法です。例えばさっきの例文で言うと「Some men are」と音源が言ったらその後ろを「Some men are」とすぐさま発音します。(もっと知りたい方は、検索してみてください。)
〇ポイント1:結構むずかしい
ものすごく効果がある練習法であることは間違いありませんが、結構難しいです。
シャドーイングは本来、テキストや教科書を見ないで音だけを聞いてついていく練習法です。ですから、リスニングがあまりできず、発音練習をしてこなかった人がいきなりシャドーイングをすると、全然ついていけずに挫折する可能性がすごく高い方法でもあります。
〇ポイント2:難易度を下げて練習する
やってみて「自分には厳しいんじゃないか」と思った場合、少し難易度を下げることもできます。
その方法は、シャドーイングをするときに、教科書や参考書を見ながらするやり方です。
文字というサポートがあるので、普通のシャドーイングよりは圧倒的にやりやすくなります。
2.マンブリング
聞いたことがある人が少ないと思います。マンブリングというのは、モゴモゴと発音するような練習です。
普通にシャドーイングをすると、音源の音と自分の声が混ざるため、やりづらいことがあります。そこで、自分の声の大きさをすごく落として、もごもごと小さい声でやると、音源を聞くことに集中できるようになります。
テキストなしで音だけ聞いて、シャドーイングができるようになるのが最終的な目標ですが、それが難しい場合には、テキストを使ったり、マンブリングをしてみるのがおすすめです。
最終的に、色々な音源を使ってシャドーイングができるようになれば、気づいたときには以前より音が聞こえるようになっていたり、意味がわかるようになっていると思います。
おわりに
以上、リスニング対策の解説をしました。
究進塾では、過去問や予想問題などを使いながら、基礎学力到達度テストの対策をお手伝いしています。
受講にご興味のある方、疑問や気になることがある方は「無料体験授業をご希望の方」のフォームからお気軽にお問い合わせください。
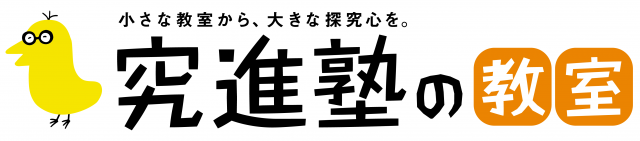







 Twitter
Twitter YouTube
YouTube LINE
LINE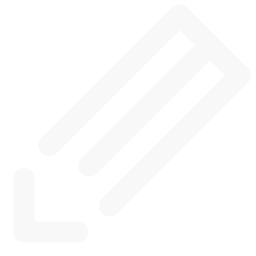 体験授業申込
体験授業申込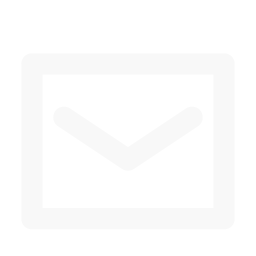 お問い合わせ
お問い合わせ